情報解禁となりましたのでいよいよ書くことが出来ます。
先日のAMD勉強会最大のテーマであったのがこのドライバを含むスイートソフト、Catalystの新バージョンでした。その名はOmega。なにかATI時代に非純正ドライバであったオメガドライバを思い出させる名前ですが、実は勉強会当日までこの名は秘密であり、届いたメールでは"Catalyst X"という名でした。今までの数字のバージョン以外に名がついているところからもわかる通り、従来以上の大型バージョンアップとなっています。また今回このドライバに関して説明していただいた方はAMD本社の方々です。
![]()
勉強会が緊急の開催となったのは彼らの来日に合わせたから、と見て間違いないでしょう。それほどの重要なバージョンアップなのです。とはいえ、その多くはゲームを想定したものです。APUが高機能化し、IntelCPUを使った場合でも内蔵GPUで一般的な用途では支障のない現在、あえていまやPCパーツの中でもっとも高価であるグラフィックボードを追加購入する目的の多くはゲームを快適に遊ぶためであると考えられるからです。当初予定されていた解禁日であった5日に海外で誤って先走り情報を公開したサイトのデータが流通しているだけにもう新鮮さはないかも知れませんが、動画派であるわれわれも注目に値すべき項目もいくつか含まれていますので、知っておいて損はありません。2002年のATI時代以来、すでに8000万もダウンロードされているCatalystの機能とは?
現在AMDのゲーム用途の文字通りの中核はMantleです。DirectX以上にGPUの性能を直接引き出すこのAPIは、たとえばThiefというタイトルではDirectX比で最大66%の速度アップを実現できますが、実はまだ完成ではなく、ある意味ゲームと二人三脚で進化し続けるAPIであるのです。そのため、EARTH BEYONDのようにベータ版を使って初めてMantleが有効になるゲームも存在します。それを含めて登録してあるゲームメーカーは10社、タイトルは20ほどではありますが、利用を想定して登録してあるゲームメーカーは100社に至っており、少なくともDirectXが12になるまでMantleは多くのタイトルに使われ続けるでしょう。その多くは海外のメーカーですが、国内メーカーでもPC向け3Dゲームタイトルに力を入れているカプコンは現在Mantleを中核としたゲームエンジンをテスト中で、これは同じくAMD製APUを搭載したPS4やX BOX oneと同じエンジンになるとのことです。つまり近い将来カプコンのWindowsPC向けゲームはRADEONに最適化されます。また、Matle活用タイトルではないようですがスクエア・エニックスのドラゴンクエストXはAMDとのタイアップでバンドルされたPCが発売されており、AMDのPCゲーム戦略の一端を担っています。海外製ゲームはちょっと・・・という人もこれらのソフトメーカーならおなじみでしょうから抵抗なくプレイできるかもしれません。
そして新バージョンのOMEGAです。これは主に3つの項目からなりたっています。
1.パフォーマンス改善
2.新機能
3.バグフィックス
です。パフォーマンス改善はドライバの大きな目的の一つですから当然でしょう。新機能としては
・ディティールエンハンスメント
SDの静止画・映像をディスプレイに拡大表示を行う場合、デティールアップをしながらノイズ除去を行い、単純なアップスケールでない拡大を行う機能です。また、1080Pを4Kに拡大する場合は「アダプティブアップスケーリング」と呼んで区別しており、AMDいわく「4Kネイティブ映像に匹敵する」映像にできるとのことです。ただし、4K対応は285・290型番のRADEONのみとなっており、APUではできない模様です。よく言えば単純な拡大表示ではないと言うことです。
・FruidMotionVideo
まぁこれはすでに実現していますが、これもCatalyst OMEGAの機能として説明を受けました。ということは、今までよりも高機能化しているのかも知れません。また、RADEON得意の画質改善も改良が見られるようです。
・フレームレイシング
クロスファイヤー・デュアルグラフィックと言った複数GPUを同時に利用することでゲームのパフォーマンスをアップさせる機能がRADEONにはありますが、従来はこの複数GPUの機能が異なると性能の高い方がムダになりました。これを調整し、両者の連携をスムーズに行えるというものです。
・バーチャルスーパーレゾリューション
さっきのアップスケーリングの逆で、4K表示モードのゲームを2Kディスプレイに表示させる機能です。アクションゲームはともかくストラテジーやシミュレーションゲームは大きさ解像度のディスプレイを利用するときその分表示される情報を増やし、マップを大きくするために使われます。その4K分の情報を2Kディスプレイで表示するというものです。当然細部がつぶれますが、そこをGPUで調整して元の情報を再現するようです。ただし、4Kビデオ出力を想定した機能のため、やはり285X・290なRADEONがターゲットとなります。
・5Kディスプレイ・24ディスプレイ対応
表示だけなら4Kにはすでに対応していますが、OMEGAで5Kでも表示出来るようになるとのことです。また、マルチディスプレイも最大24台まで使えるとのことですが、これはまぁ我々個人ユーザーには関係のない話でしょう。一度ニューヨークのタイムズ・スクエアで実際に24台のマルチディスプレイを使ったデモが行われたことがあるそうです。
バグフィックスとは、品質主義の基づく動作の安定性を示すものです。アメリカの話のようですが、多くのRADEONを利用している人々に対して非常にシンプルな質問を投げかけることがありました。その中身は
「Catalystの問題はなんですか?」
それであがった問題点のうち、少なくともトップ10に入る項目に関しては修正済みですべて対処できた、ということです。具体的に何が上がったかまでは教えてもらえませんでしたが、後日英語のサイトで公開されるということです。
最後に、会でももっとも注目を浴びた機能を紹介しましょう。と、言ってもその多くはすでに知られているのですが、それがFreeSyncです。先行するNvidiaのG-Syncと似た機能ですが、G-Syncがディスプレイに専用チップを搭載する必要があるのに対し、FreeSyncはソフトウェアさえ対応させればチップは必要ないところが大きな差です。なおFreeSyncはAMDの使う呼び名ですが、ディスプレイ標準規格団体であるVESAによって「Adaptive-Sync」の名で定義されることも決まっています。
機能的な優劣に関しては、まだ製品が存在しませんので知ることはできません。さすがに専用チップをわざわざ必要とするG-Syncの方が速度面で若干有利ではないか? という気もしますがライセンス料も不要なため、断然安く済ませられるのはFreeSyncでしょう。
ここで重要な話を聞いてきました。他にFreeSyncのG-Syncに対する優位点として「G-Syncはゲーム用であるため30~144Hzまでしか対応していないが、FreeSyncはもっと広い幅にも対応している。たとえばBDに最適な24Hzにもだ」の一言(を、英語で語ったのを翻訳したもの)をはっきりと聞いてきました。現状のディスプレイは基本60Hz固定ですから24p映像を再生する場合、同期しない水増しフレームをはさむ必要があるため、動きがカクカクすることがあります。その動きの悪さを解消する解答の一つがFluidMotionVideo機能であることはすでに書きましたが、FreeSyncは動的にディスプレイのリフレッシュレートを変更することでコマごとの表示時間を同一にすることで対応する、もう一つの答えです。ある意味出たばかりのFluidMotionVideo機能の否定にもつながりかねませんが、それをAMDが出したというのが面白いです。FluidMotionVideoの効果は楽しいですが、映像の質感が変わってしまうことに違和感を覚える人もいるでしょう。FreeSyncならそんなことはありません。ユーザーはソフトや好みに応じて好きな方を選べるのです。また、ディスプレイの動作状態によってCPUのようにリフレッシュレートを低くを抑える時間をとることでディスプレイの消費電力を抑える効果もあるそうです。G-Sync対応は例外なくゲーム向けディスプレイですが、FreeSyncはそうでないビジネス向けや動画向けディスプレイが採用してもおかしくないのです。また、こっそりノート向けの技術としても期待されます(一部はすでに取り入れられているとのことです)。
このようなFreeSyncはOmega以降で可能になります。もちろんRADEONのハイクラスだけでなく、APUでも(おそらくKaveriなら)対応できます。接続は現状ではDisplayPort1.2が対象ですが、HDMI接続でも技術的には可能とのこと。
肝心の対応ディスプレイなんですが、現状で公表できるディスプレイメーカーはサムソンだけ。ですがご存知の通りサムソンは日本ではディスプレイ事業を行っていないため、日本だけFreeSyncをつかるようになる日が遅れることになります。他にも対応を検討しているディスプレイメーカーはあるようですが、これは公表してもらえませんでした。なるべく少ないタイムラグで日本でも利用できるようになるよう、祈るしかないですね。
どちらかと言うと単体RADEON向けの機能アップが多いという印象のCatalystOmegaではありますが、APUユーザーこそ積極的に入れるべきです。CatalystはAMDシステム全体に関わるスイートであるため、APUの場合GPU部分だけでなくCPU部分まで含む全体のパフォーマンスアップが期待出来るからです。とはいえ、この肝心のCatalystOmegaは9日14時現在、まだAMDサイトにはアップされていないようです(※15時に確認したら、Omegaの名ではありませんが14.12がアップされていました!)。ベンチマークで単純に計るだけでない機能アップが多く盛り込まれたOmegaは、ちょっと先の未来を期待させるものになっていると思います。
先日のAMD勉強会最大のテーマであったのがこのドライバを含むスイートソフト、Catalystの新バージョンでした。その名はOmega。なにかATI時代に非純正ドライバであったオメガドライバを思い出させる名前ですが、実は勉強会当日までこの名は秘密であり、届いたメールでは"Catalyst X"という名でした。今までの数字のバージョン以外に名がついているところからもわかる通り、従来以上の大型バージョンアップとなっています。また今回このドライバに関して説明していただいた方はAMD本社の方々です。
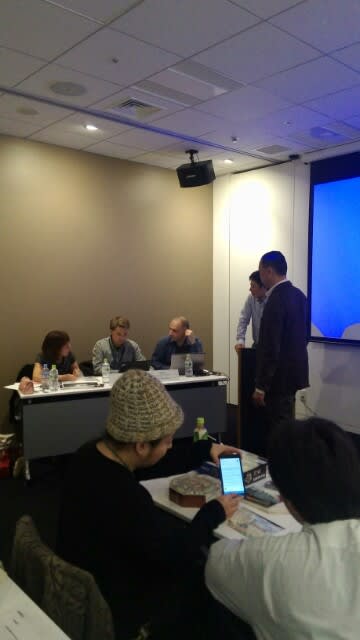
勉強会が緊急の開催となったのは彼らの来日に合わせたから、と見て間違いないでしょう。それほどの重要なバージョンアップなのです。とはいえ、その多くはゲームを想定したものです。APUが高機能化し、IntelCPUを使った場合でも内蔵GPUで一般的な用途では支障のない現在、あえていまやPCパーツの中でもっとも高価であるグラフィックボードを追加購入する目的の多くはゲームを快適に遊ぶためであると考えられるからです。当初予定されていた解禁日であった5日に海外で誤って先走り情報を公開したサイトのデータが流通しているだけにもう新鮮さはないかも知れませんが、動画派であるわれわれも注目に値すべき項目もいくつか含まれていますので、知っておいて損はありません。2002年のATI時代以来、すでに8000万もダウンロードされているCatalystの機能とは?
現在AMDのゲーム用途の文字通りの中核はMantleです。DirectX以上にGPUの性能を直接引き出すこのAPIは、たとえばThiefというタイトルではDirectX比で最大66%の速度アップを実現できますが、実はまだ完成ではなく、ある意味ゲームと二人三脚で進化し続けるAPIであるのです。そのため、EARTH BEYONDのようにベータ版を使って初めてMantleが有効になるゲームも存在します。それを含めて登録してあるゲームメーカーは10社、タイトルは20ほどではありますが、利用を想定して登録してあるゲームメーカーは100社に至っており、少なくともDirectXが12になるまでMantleは多くのタイトルに使われ続けるでしょう。その多くは海外のメーカーですが、国内メーカーでもPC向け3Dゲームタイトルに力を入れているカプコンは現在Mantleを中核としたゲームエンジンをテスト中で、これは同じくAMD製APUを搭載したPS4やX BOX oneと同じエンジンになるとのことです。つまり近い将来カプコンのWindowsPC向けゲームはRADEONに最適化されます。また、Matle活用タイトルではないようですがスクエア・エニックスのドラゴンクエストXはAMDとのタイアップでバンドルされたPCが発売されており、AMDのPCゲーム戦略の一端を担っています。海外製ゲームはちょっと・・・という人もこれらのソフトメーカーならおなじみでしょうから抵抗なくプレイできるかもしれません。
そして新バージョンのOMEGAです。これは主に3つの項目からなりたっています。
1.パフォーマンス改善
2.新機能
3.バグフィックス
です。パフォーマンス改善はドライバの大きな目的の一つですから当然でしょう。新機能としては
・ディティールエンハンスメント
SDの静止画・映像をディスプレイに拡大表示を行う場合、デティールアップをしながらノイズ除去を行い、単純なアップスケールでない拡大を行う機能です。また、1080Pを4Kに拡大する場合は「アダプティブアップスケーリング」と呼んで区別しており、AMDいわく「4Kネイティブ映像に匹敵する」映像にできるとのことです。ただし、4K対応は285・290型番のRADEONのみとなっており、APUではできない模様です。よく言えば単純な拡大表示ではないと言うことです。
・FruidMotionVideo
まぁこれはすでに実現していますが、これもCatalyst OMEGAの機能として説明を受けました。ということは、今までよりも高機能化しているのかも知れません。また、RADEON得意の画質改善も改良が見られるようです。
・フレームレイシング
クロスファイヤー・デュアルグラフィックと言った複数GPUを同時に利用することでゲームのパフォーマンスをアップさせる機能がRADEONにはありますが、従来はこの複数GPUの機能が異なると性能の高い方がムダになりました。これを調整し、両者の連携をスムーズに行えるというものです。
・バーチャルスーパーレゾリューション
さっきのアップスケーリングの逆で、4K表示モードのゲームを2Kディスプレイに表示させる機能です。アクションゲームはともかくストラテジーやシミュレーションゲームは大きさ解像度のディスプレイを利用するときその分表示される情報を増やし、マップを大きくするために使われます。その4K分の情報を2Kディスプレイで表示するというものです。当然細部がつぶれますが、そこをGPUで調整して元の情報を再現するようです。ただし、4Kビデオ出力を想定した機能のため、やはり285X・290なRADEONがターゲットとなります。
・5Kディスプレイ・24ディスプレイ対応
表示だけなら4Kにはすでに対応していますが、OMEGAで5Kでも表示出来るようになるとのことです。また、マルチディスプレイも最大24台まで使えるとのことですが、これはまぁ我々個人ユーザーには関係のない話でしょう。一度ニューヨークのタイムズ・スクエアで実際に24台のマルチディスプレイを使ったデモが行われたことがあるそうです。
バグフィックスとは、品質主義の基づく動作の安定性を示すものです。アメリカの話のようですが、多くのRADEONを利用している人々に対して非常にシンプルな質問を投げかけることがありました。その中身は
「Catalystの問題はなんですか?」
それであがった問題点のうち、少なくともトップ10に入る項目に関しては修正済みですべて対処できた、ということです。具体的に何が上がったかまでは教えてもらえませんでしたが、後日英語のサイトで公開されるということです。
最後に、会でももっとも注目を浴びた機能を紹介しましょう。と、言ってもその多くはすでに知られているのですが、それがFreeSyncです。先行するNvidiaのG-Syncと似た機能ですが、G-Syncがディスプレイに専用チップを搭載する必要があるのに対し、FreeSyncはソフトウェアさえ対応させればチップは必要ないところが大きな差です。なおFreeSyncはAMDの使う呼び名ですが、ディスプレイ標準規格団体であるVESAによって「Adaptive-Sync」の名で定義されることも決まっています。
機能的な優劣に関しては、まだ製品が存在しませんので知ることはできません。さすがに専用チップをわざわざ必要とするG-Syncの方が速度面で若干有利ではないか? という気もしますがライセンス料も不要なため、断然安く済ませられるのはFreeSyncでしょう。
ここで重要な話を聞いてきました。他にFreeSyncのG-Syncに対する優位点として「G-Syncはゲーム用であるため30~144Hzまでしか対応していないが、FreeSyncはもっと広い幅にも対応している。たとえばBDに最適な24Hzにもだ」の一言(を、英語で語ったのを翻訳したもの)をはっきりと聞いてきました。現状のディスプレイは基本60Hz固定ですから24p映像を再生する場合、同期しない水増しフレームをはさむ必要があるため、動きがカクカクすることがあります。その動きの悪さを解消する解答の一つがFluidMotionVideo機能であることはすでに書きましたが、FreeSyncは動的にディスプレイのリフレッシュレートを変更することでコマごとの表示時間を同一にすることで対応する、もう一つの答えです。ある意味出たばかりのFluidMotionVideo機能の否定にもつながりかねませんが、それをAMDが出したというのが面白いです。FluidMotionVideoの効果は楽しいですが、映像の質感が変わってしまうことに違和感を覚える人もいるでしょう。FreeSyncならそんなことはありません。ユーザーはソフトや好みに応じて好きな方を選べるのです。また、ディスプレイの動作状態によってCPUのようにリフレッシュレートを低くを抑える時間をとることでディスプレイの消費電力を抑える効果もあるそうです。G-Sync対応は例外なくゲーム向けディスプレイですが、FreeSyncはそうでないビジネス向けや動画向けディスプレイが採用してもおかしくないのです。また、こっそりノート向けの技術としても期待されます(一部はすでに取り入れられているとのことです)。
このようなFreeSyncはOmega以降で可能になります。もちろんRADEONのハイクラスだけでなく、APUでも(おそらくKaveriなら)対応できます。接続は現状ではDisplayPort1.2が対象ですが、HDMI接続でも技術的には可能とのこと。
肝心の対応ディスプレイなんですが、現状で公表できるディスプレイメーカーはサムソンだけ。ですがご存知の通りサムソンは日本ではディスプレイ事業を行っていないため、日本だけFreeSyncをつかるようになる日が遅れることになります。他にも対応を検討しているディスプレイメーカーはあるようですが、これは公表してもらえませんでした。なるべく少ないタイムラグで日本でも利用できるようになるよう、祈るしかないですね。
どちらかと言うと単体RADEON向けの機能アップが多いという印象のCatalystOmegaではありますが、APUユーザーこそ積極的に入れるべきです。CatalystはAMDシステム全体に関わるスイートであるため、APUの場合GPU部分だけでなくCPU部分まで含む全体のパフォーマンスアップが期待出来るからです。とはいえ、この肝心のCatalystOmegaは9日14時現在、まだAMDサイトにはアップされていないようです(※15時に確認したら、Omegaの名ではありませんが14.12がアップされていました!)。ベンチマークで単純に計るだけでない機能アップが多く盛り込まれたOmegaは、ちょっと先の未来を期待させるものになっていると思います。