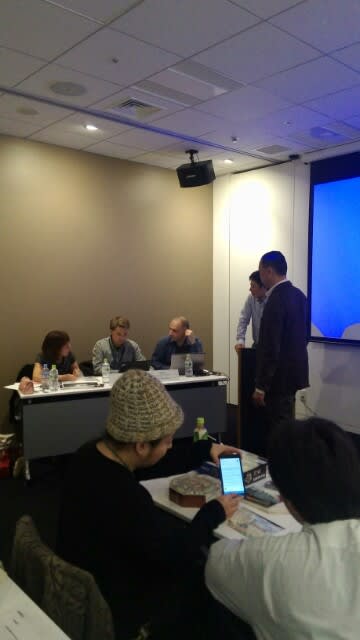先日行われましたAMDのブロガー勉強会。この会では得た情報のテストを対象ブロガーが行える環境を提供することと新製品のレビューを目的として、我々ブロガーは組み立て用PCのパーツをおみやげとしていただけることになっています。今回いただいたのは先日も書きました通りAPUとしてKeveriとしては上から二番目となるA10-7800、それを装着するマザーボードとしてMSI社製のA68HM-P33です。
![]()
後日秋葉原のショップを巡って同マザーを見つけましたが、税抜きで5500円ほどで売っている店がありました。発売開始がこの11月15日ですから、最初から非常に安い値段で売られている商品となります。すでにAPUのブロガー勉強会は三回目ですが、以前の二回はいずれも発売開始時期としては高機能なマザーボードを提供いただいた(感謝しています)ことを考えると少々意外な提供です。これは採用されたチップセット、A68HがAMD社製としては最新のものであり、まだ世間的評価を受けていないものであるということが挙げられます。また、ここでバラしますが実は最初に今回の勉強会の話をいただいたとき、提供いただけるAPUは最廉価のA6-7400Kという話でした。別に書きました通りA6-7400Kは値下げが行われたばかり。テーマの一つとして安くなったAPUと低価格向け新チップセット搭載マザーの組み合わせで十分使える低価格PCを試してほしいという狙いがAMDにはあったのでしょう。安いA68HM-P33とA6-7400Kの組み合わせならバランスは取れています。ところが二度目のメールで「よりハイエンドのKaveriAPU」に変更になったと連絡があり、実際にA10-7800になりました。これはA6-7400Kは勉強会のテーマの一つであるFluid Motion Videoを試すことができないこと、ほかのテストを行うにも少々力不足である点が問題としてあるため、変更になったと思われます。ちなみに希望者にはPowerDVD14Ultraの提供も行われましたが、ソフトのレビューが条件だったので、わたしには今更であるため辞退しています。
さてこのマザーに使われるA68H(ちなみにHの付かないA68というチップセットがモバイル向けにありましたので要区別)チップセット。A68HM-P33の価格からしてこれまでの低価格向けチップセットA58を置き換える存在と見て良いでしょう。違いは上級のA88Xと同じくUSB3.0とSATA3.0(6Gb)をサポートした点にあります。MSIの資料によりますと、特にUSB3.0において外付けのチップで対応した場合と比べ、27%以上の高速化を実現しているとのことです。ただし差別化のためもあってサポート数はUSB3.0が2つ、SATA3.0が4つまで。A68HM-P33もそれにあわせてUSB3.0が2つ、SATAは4つ搭載されています。USB2.0はもちろん別にバックで4つ、フロント向けに4つが搭載されていますので、機器に応じて使い分ければ数が不足することはそうそうないでしょう。SATAは少々不足するかも知れません。マザーにはSATA5/6搭載用コネクタのパターンが残っていますが、別チップで増設すればそれだけ価格がアップするため、見送られたのでしょう。幸い同マザーはPCI-Express3.0x16x1、PCI-Express2.0x1x3とMicroATXの拡張スロット数の上限である4つを搭載していますので、増設ボードを積むには困りません。APUですからPCI-Expressx16にグラボを挿さなくても十分なシステムが組めますので一つくらいPCIの方が良かったようにも思いますが、これから組むのなら全部PCI-Expressでも問題ないでしょう。
一方低価格向けらしくメモリスロットは2つしかなく、対応はDDR3-2133まで、しかもOCでの対応となっています。ただ、少なくともBIOSをアップデートしたあとならXMPを読み込ませればそのまま2133で動作してくれるうえ、今のところそれが原因と思われる不安定さは経験していないため、OC対応を気にする必要はありません。メモリもなんだかんだ言って4つ使うと不安定要素に繋がりかねませんから2しか使わないケースは多いですしね。むしろ少なくした分小型化して組み立てがしやすくなった良さもあります。問題はメモリとの相性でデュアルチャンネルがうまくいかず、シングルになってしまった場合、他のスロットが活用できない点ですが、これは運に頼るしかないです。ちなみにわたしはAMDメモリのDDR3-2133で無事デュアルになってくれました。
![]()
左は今回の新システムの代わりにに外すことになった、以前の勉強会でいただいたA10-6800k+F2A85-M PROです。AMD向けMicroATXとしては豪華高機能なマザーでしたがFM2までしか対応できないため、Richlandとともに外すことになりました。良いマザーなだけに比較的大きく、小型のケースに入れると水平接続のSATAが使えなくなる欠点がありましたが、A68HM-P33は見て分かる通り幅が非常に短いため、MicroATXの装着できるケースならどんなものでも楽々と収まります。大変組み立てやすいマザーでした。
ただし、低価格ゆえに搭載機能とは別に割り切ったものも多くあります。なにより本機にはマニュアルが付いていません。他マザー兼用のペーパー説明しか付いていないので、電源やリセットコネクタの差し込みなどはマザーボードに印刷されたパターンを読みながら組む必要があります。また、CMOSをクリアするジャンパピンに至っては何の説明もないため、見ただけで「あ、これか」と分かる程度の知識が必要になります(ちなみにボタン電池のすぐ近くのジャンパピンです)。つまり安いと言っても初心者向けとかではなく(つーかわたしは初心者はなるべく高価格高機能なものを使うべきだと思ってますが、どうしても「低価格小型が初心者向け」とこっちに言わせたがる人もいますので)、何台も組み立てを経験してマニュアルを見ずに組み立てに取りかかる人向けなのです。また、残念ながらディスプレイの出力はDIV-DとD-SUBだけ。価格と考えれば仕方ないのですがボード上にパターンが残るDisplayPortもありません。そっちはまだしもHDMIは欲しかった。ちなみに相性もあるかも知れませんが内蔵DVI-DにHDMI変換コネクタを通してディスプレイのHDMI端子に繋いでみたら映りませんでした。
そういった省略はありますが耐久性といった基本性能を重視した作りに妥協はなく、MSIによると
・温度・ESD・放電・EMI・高温への耐性向上「ミリタリークラス・エッセンシャルズ」
・信頼性と耐久性の証「ミリタリークラス4」
という同社の掲げる二つのミリタリークラス水準を満たしており、静電気を抑え、高温環境でも安定性を落とさず、極端な条件下でも安定動作するそうです。もちろんだからと言ってそういう環境を用意して実験することはしませんが。
その代わりに別の"ウリ"を試しましょう。MSI提供による本マザーのウリは高速起動とそのサポートにあるようです。もちろんWindows8によるUEFI環境は必須。ところがわたし、今回使うシステムはTrinityから使い続けている(つまり勉強会でいただいたセットのリプレースを繰り返している)もので元はWindows7だったのを8.1にアップデートして使っていたため、起動にUEFIを使ってないんです。ちなみにUEFI起動をサポートしていない状態でこのマザーの機能である"FAST BOOT"を使うとキーボード入力も受け付けず、起動もしないというニッチもサッチもいかないブルドッグ状態になってしまうのでCMOSをクリアするしかなくなってしまいます(なので必ずCMOSのジャンパピンの位置は確認してください)。しょうがありません。今までの環境に別れを告げ、UEFIで全部入れ直しましょう。ちなみにこれを決断する前に一度マザー交換で認証しなおし、OSのクリーンアップでまた再認証と短期間に二度の認証し直しをしたため、マイクロソフトの電話サポートに怪しまれました(笑)。しょうがないじゃないかよ~。好きで何度もサポートに電話してるわけじゃないし。そうそう、今ならセキュリティもあるので8から8.1にバージョンアップするのは必須ですが、Windows8のインストール用起動ディスクでWindows8.1を修復しようとしたりリフレッシュしようとしたりしても「ロックが掛かっています」のメッセージが返ってくるだけで出来ませんので、なるべくすっぴんに近い8.1での回復用メディアをUSBメモリで作っておくのを忘れないように。
2日掛かりましたが一から入れたWindows8.1に各種ソフトも再インストールした新環境への移行は無事成功しました。このマザーのウリは先に書いたとおり独自の"FAST BOOT"による高速起動。Windows8/8.1のUEFI起動は利用するハードの一部をBIOS起動時に無効化し、有効化を後回しにすることで起動を高速にするものですが、FAST BOOTは「一部」の例外となっている機能まで無効化してしまうモードです。その際電源ON時に画面右下に表示される数字・英文字による状態を示すカウンター(A2などと表示され、最終的に99になる)がいきなり99の状態で起動します。省略されるのはこの「フルスクリーンロゴ」などが起動する合間のため、電源ON時は起動の速さを体感にしくいものとなっています。その代わり我々がよく使う休止状態からの復帰では何かタガが外れたかのように驚異的なスピードで復帰を果たします。わたしはこのPCにHDDをたくさん繋いでいたので以前はレガシー環境であることも含めて休止状態からの復帰が遅かったのですが、ソレと比べるとバカみたいに速いので間違えてスタンバイにしたのではないかと疑ったくらいです。逆にスタンバイにはうまくならず、失敗したのですが・・・。これだけ休止からの復帰が速いともうスタンバイなど不要でしょう。ちなみにわたしはPT3+MarvelチップのSATAボード+SiliconチップのSATAボードと三枚挿していますが休止への移行も復帰も問題なく利用できます。
ただし、FAST BOOTはより多くの機能を起動時に停止させるため、UEFIメニューを起動時にキーボードのDELキーで起動させることが不可能になります。そのため、MSIではFAST BOOTをWindows上で有効無効に出来る機能と、一時的にFAST BOOTどころかUEFI起動も無効にして自動的にUEFIメニューを立ち上げてくれる再起動を行ってくれる機能を持った専用ツールが付いてきます。一度同マザーでWindows8.1で環境を作ってしまえば、もうメニューのためにDELキーを連打する必要はありません。
ただ、BIOSには若干クセがあります。HDDなどがちゃんと全部接続されているかどうかが起動HDDの選択部分からしか確認出来ませんし、振られるSATAの番号が一番若いものが他のマザーの"0"ではなく"1"になっているのです。どうして0にならないのかと何度も接続しなおしてしまいました。ただ、UEFIのBOOTManagerの扱いではちゃんと0になります。ここら辺他社のマザーになれていると混乱するので注意。
また、最近では珍しく省電力化ツールなどもなかったようですが、A10-7800は標準の省電力機能でもまずまず優秀なのであえてツールに頼る必要もないかと思います。それゆえ、DDR3が2133までであることと合わせ、最高性能のKaveriであるA10-7850Kと合わせるにはA68HM-P33は必要十分とは言えません。が、A10-7800はもちろんA8-7600、それに本来の組み合わせであったA6-7400Kと言ったデフォルトTDP65Wモデルならこれで十分、もちろんcTDPも使えます。テレビと繋いで動画出力やマルチディスプレイ化と言った表示機能を重視したPCには向きませんが、それでもDVI-Dで2560x1600・D-SUBでも2048x1280まで60Hzまで出せますのでシングルディスプレイで普通に遣うには十分。足りないところは手持ちの機材と自分の知識で補えるから安くKaveriで普段使い用PCを組みたいという人にはうってつけでしょう。正直この爆速復帰になれると、もっと高機能なCPUを使っていてもOSがWindows7なPCは使いたくなくなってきます、起動も復帰も遅くて。

後日秋葉原のショップを巡って同マザーを見つけましたが、税抜きで5500円ほどで売っている店がありました。発売開始がこの11月15日ですから、最初から非常に安い値段で売られている商品となります。すでにAPUのブロガー勉強会は三回目ですが、以前の二回はいずれも発売開始時期としては高機能なマザーボードを提供いただいた(感謝しています)ことを考えると少々意外な提供です。これは採用されたチップセット、A68HがAMD社製としては最新のものであり、まだ世間的評価を受けていないものであるということが挙げられます。また、ここでバラしますが実は最初に今回の勉強会の話をいただいたとき、提供いただけるAPUは最廉価のA6-7400Kという話でした。別に書きました通りA6-7400Kは値下げが行われたばかり。テーマの一つとして安くなったAPUと低価格向け新チップセット搭載マザーの組み合わせで十分使える低価格PCを試してほしいという狙いがAMDにはあったのでしょう。安いA68HM-P33とA6-7400Kの組み合わせならバランスは取れています。ところが二度目のメールで「よりハイエンドのKaveriAPU」に変更になったと連絡があり、実際にA10-7800になりました。これはA6-7400Kは勉強会のテーマの一つであるFluid Motion Videoを試すことができないこと、ほかのテストを行うにも少々力不足である点が問題としてあるため、変更になったと思われます。ちなみに希望者にはPowerDVD14Ultraの提供も行われましたが、ソフトのレビューが条件だったので、わたしには今更であるため辞退しています。
さてこのマザーに使われるA68H(ちなみにHの付かないA68というチップセットがモバイル向けにありましたので要区別)チップセット。A68HM-P33の価格からしてこれまでの低価格向けチップセットA58を置き換える存在と見て良いでしょう。違いは上級のA88Xと同じくUSB3.0とSATA3.0(6Gb)をサポートした点にあります。MSIの資料によりますと、特にUSB3.0において外付けのチップで対応した場合と比べ、27%以上の高速化を実現しているとのことです。ただし差別化のためもあってサポート数はUSB3.0が2つ、SATA3.0が4つまで。A68HM-P33もそれにあわせてUSB3.0が2つ、SATAは4つ搭載されています。USB2.0はもちろん別にバックで4つ、フロント向けに4つが搭載されていますので、機器に応じて使い分ければ数が不足することはそうそうないでしょう。SATAは少々不足するかも知れません。マザーにはSATA5/6搭載用コネクタのパターンが残っていますが、別チップで増設すればそれだけ価格がアップするため、見送られたのでしょう。幸い同マザーはPCI-Express3.0x16x1、PCI-Express2.0x1x3とMicroATXの拡張スロット数の上限である4つを搭載していますので、増設ボードを積むには困りません。APUですからPCI-Expressx16にグラボを挿さなくても十分なシステムが組めますので一つくらいPCIの方が良かったようにも思いますが、これから組むのなら全部PCI-Expressでも問題ないでしょう。
一方低価格向けらしくメモリスロットは2つしかなく、対応はDDR3-2133まで、しかもOCでの対応となっています。ただ、少なくともBIOSをアップデートしたあとならXMPを読み込ませればそのまま2133で動作してくれるうえ、今のところそれが原因と思われる不安定さは経験していないため、OC対応を気にする必要はありません。メモリもなんだかんだ言って4つ使うと不安定要素に繋がりかねませんから2しか使わないケースは多いですしね。むしろ少なくした分小型化して組み立てがしやすくなった良さもあります。問題はメモリとの相性でデュアルチャンネルがうまくいかず、シングルになってしまった場合、他のスロットが活用できない点ですが、これは運に頼るしかないです。ちなみにわたしはAMDメモリのDDR3-2133で無事デュアルになってくれました。

左は今回の新システムの代わりにに外すことになった、以前の勉強会でいただいたA10-6800k+F2A85-M PROです。AMD向けMicroATXとしては豪華高機能なマザーでしたがFM2までしか対応できないため、Richlandとともに外すことになりました。良いマザーなだけに比較的大きく、小型のケースに入れると水平接続のSATAが使えなくなる欠点がありましたが、A68HM-P33は見て分かる通り幅が非常に短いため、MicroATXの装着できるケースならどんなものでも楽々と収まります。大変組み立てやすいマザーでした。
ただし、低価格ゆえに搭載機能とは別に割り切ったものも多くあります。なにより本機にはマニュアルが付いていません。他マザー兼用のペーパー説明しか付いていないので、電源やリセットコネクタの差し込みなどはマザーボードに印刷されたパターンを読みながら組む必要があります。また、CMOSをクリアするジャンパピンに至っては何の説明もないため、見ただけで「あ、これか」と分かる程度の知識が必要になります(ちなみにボタン電池のすぐ近くのジャンパピンです)。つまり安いと言っても初心者向けとかではなく(つーかわたしは初心者はなるべく高価格高機能なものを使うべきだと思ってますが、どうしても「低価格小型が初心者向け」とこっちに言わせたがる人もいますので)、何台も組み立てを経験してマニュアルを見ずに組み立てに取りかかる人向けなのです。また、残念ながらディスプレイの出力はDIV-DとD-SUBだけ。価格と考えれば仕方ないのですがボード上にパターンが残るDisplayPortもありません。そっちはまだしもHDMIは欲しかった。ちなみに相性もあるかも知れませんが内蔵DVI-DにHDMI変換コネクタを通してディスプレイのHDMI端子に繋いでみたら映りませんでした。
そういった省略はありますが耐久性といった基本性能を重視した作りに妥協はなく、MSIによると
・温度・ESD・放電・EMI・高温への耐性向上「ミリタリークラス・エッセンシャルズ」
・信頼性と耐久性の証「ミリタリークラス4」
という同社の掲げる二つのミリタリークラス水準を満たしており、静電気を抑え、高温環境でも安定性を落とさず、極端な条件下でも安定動作するそうです。もちろんだからと言ってそういう環境を用意して実験することはしませんが。
その代わりに別の"ウリ"を試しましょう。MSI提供による本マザーのウリは高速起動とそのサポートにあるようです。もちろんWindows8によるUEFI環境は必須。ところがわたし、今回使うシステムはTrinityから使い続けている(つまり勉強会でいただいたセットのリプレースを繰り返している)もので元はWindows7だったのを8.1にアップデートして使っていたため、起動にUEFIを使ってないんです。ちなみにUEFI起動をサポートしていない状態でこのマザーの機能である"FAST BOOT"を使うとキーボード入力も受け付けず、起動もしないというニッチもサッチもいかないブルドッグ状態になってしまうのでCMOSをクリアするしかなくなってしまいます(なので必ずCMOSのジャンパピンの位置は確認してください)。しょうがありません。今までの環境に別れを告げ、UEFIで全部入れ直しましょう。ちなみにこれを決断する前に一度マザー交換で認証しなおし、OSのクリーンアップでまた再認証と短期間に二度の認証し直しをしたため、マイクロソフトの電話サポートに怪しまれました(笑)。しょうがないじゃないかよ~。好きで何度もサポートに電話してるわけじゃないし。そうそう、今ならセキュリティもあるので8から8.1にバージョンアップするのは必須ですが、Windows8のインストール用起動ディスクでWindows8.1を修復しようとしたりリフレッシュしようとしたりしても「ロックが掛かっています」のメッセージが返ってくるだけで出来ませんので、なるべくすっぴんに近い8.1での回復用メディアをUSBメモリで作っておくのを忘れないように。
2日掛かりましたが一から入れたWindows8.1に各種ソフトも再インストールした新環境への移行は無事成功しました。このマザーのウリは先に書いたとおり独自の"FAST BOOT"による高速起動。Windows8/8.1のUEFI起動は利用するハードの一部をBIOS起動時に無効化し、有効化を後回しにすることで起動を高速にするものですが、FAST BOOTは「一部」の例外となっている機能まで無効化してしまうモードです。その際電源ON時に画面右下に表示される数字・英文字による状態を示すカウンター(A2などと表示され、最終的に99になる)がいきなり99の状態で起動します。省略されるのはこの「フルスクリーンロゴ」などが起動する合間のため、電源ON時は起動の速さを体感にしくいものとなっています。その代わり我々がよく使う休止状態からの復帰では何かタガが外れたかのように驚異的なスピードで復帰を果たします。わたしはこのPCにHDDをたくさん繋いでいたので以前はレガシー環境であることも含めて休止状態からの復帰が遅かったのですが、ソレと比べるとバカみたいに速いので間違えてスタンバイにしたのではないかと疑ったくらいです。逆にスタンバイにはうまくならず、失敗したのですが・・・。これだけ休止からの復帰が速いともうスタンバイなど不要でしょう。ちなみにわたしはPT3+MarvelチップのSATAボード+SiliconチップのSATAボードと三枚挿していますが休止への移行も復帰も問題なく利用できます。
ただし、FAST BOOTはより多くの機能を起動時に停止させるため、UEFIメニューを起動時にキーボードのDELキーで起動させることが不可能になります。そのため、MSIではFAST BOOTをWindows上で有効無効に出来る機能と、一時的にFAST BOOTどころかUEFI起動も無効にして自動的にUEFIメニューを立ち上げてくれる再起動を行ってくれる機能を持った専用ツールが付いてきます。一度同マザーでWindows8.1で環境を作ってしまえば、もうメニューのためにDELキーを連打する必要はありません。
ただ、BIOSには若干クセがあります。HDDなどがちゃんと全部接続されているかどうかが起動HDDの選択部分からしか確認出来ませんし、振られるSATAの番号が一番若いものが他のマザーの"0"ではなく"1"になっているのです。どうして0にならないのかと何度も接続しなおしてしまいました。ただ、UEFIのBOOTManagerの扱いではちゃんと0になります。ここら辺他社のマザーになれていると混乱するので注意。
また、最近では珍しく省電力化ツールなどもなかったようですが、A10-7800は標準の省電力機能でもまずまず優秀なのであえてツールに頼る必要もないかと思います。それゆえ、DDR3が2133までであることと合わせ、最高性能のKaveriであるA10-7850Kと合わせるにはA68HM-P33は必要十分とは言えません。が、A10-7800はもちろんA8-7600、それに本来の組み合わせであったA6-7400Kと言ったデフォルトTDP65Wモデルならこれで十分、もちろんcTDPも使えます。テレビと繋いで動画出力やマルチディスプレイ化と言った表示機能を重視したPCには向きませんが、それでもDVI-Dで2560x1600・D-SUBでも2048x1280まで60Hzまで出せますのでシングルディスプレイで普通に遣うには十分。足りないところは手持ちの機材と自分の知識で補えるから安くKaveriで普段使い用PCを組みたいという人にはうってつけでしょう。正直この爆速復帰になれると、もっと高機能なCPUを使っていてもOSがWindows7なPCは使いたくなくなってきます、起動も復帰も遅くて。